|
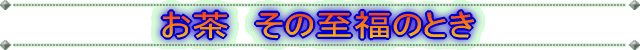
夏目漱石の「草枕」
お茶関係の本には、よく夏目漱石の「草枕
 」の一文が引用されています。 」の一文が引用されています。
「草枕」は、明治三十九年九月に「新小説」に発表されました。
この小説の中程に、主人公の画家が、ある老人にお茶に呼ばれる場面があります。
(老人は「朱泥の急須」から、「緑を含む琥珀色の玉液」を「2〜3滴ずつ」茶碗の底へ
したたらす。
茶の量は「三、四滴」で茶碗は頗る大きい。)とあるように、この小説のなかで、老人は、
大きめの茶碗にほんの三、四滴、「緑を含む琥珀色」のお茶をいれます。
この記述により、「草枕」が発表された明治三十九年以前、当時の文人や知識人のあいだに、
親しい友人を招いてお茶会を開き、名器でもてなすことが行われていたことがわかります。
そして、朱泥の急須から、やや大振りの青木木米の茶碗に緑を含む琥珀色のお茶を三四滴
いれています。
このことは何を意味するのかといいますと、明治中期頃流行っていたお茶は、「緑を含む
琥珀色」であり、その量は、「三四滴」という少量であったということです。
続いて、茶の味についての記述を次にあげます。多くの出版物に引用されているので御存知
の方も多いと思いますが、お茶の味をこれほど的確に表現した文章はないと思いますので、
その部分のみを抜粋しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
[茶碗を下へ置かないで、そのまま口へつけた。濃く甘く、湯加減に出た、重い露を、舌の先へ
一しずくずつ 落として味わって見るのは閑人適意の韻事である。
普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。舌頭へぽたりと載せて、
清いものが四方へ散ればの咽喉へ下るべき液は殆どない。只馥郁たる 匂が食道から胃の
なかへ沁み渡るのみである。歯を用いるは卑しい。水はあまりに軽い。玉露に至っては
濃かなる事、淡水の境を脱して、顎を疲らす程の硬さを知らず。結構な飲料である。眠られぬ
と訴うるものあらば、眠らぬも、茶を用いよと勧めたい。]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
まだ学生の頃、この小説をはじめて読んだとき、正直言って信じられませんでした。
それまで、父の遺してくれた煎茶道具を使って、父のやりかたを思い出しながら、煎茶を
楽しんでいましたが、それまで一度もこの小説にあるような感動を味わったことがなかった
からです。
大変な貧乏学生でしたので、僅かなアルバイト代を貯めて思い切って高価なお茶を買って
きては試してみるのですが、値段が高くなればなるほど、味は薄く、香りもおとなしいものと
なってゆき、この小説の表現とは程遠いものでした。
やはり、夏目漱石は、本当にあったことを書いたのではなく、如何に名文であっても所詮
彼の創作であり、それを鵜呑みにした私が愚かであったものと、ひとりで納得してこの小説の
ことはしばらく忘れていました。
ところが数年の後、仕事で新潟へ立ち寄ったとき、何気なく買った「やぶ北の深蒸し茶」に
であったことで「草枕」のあの一文が嘘ではなかったことがわかったのです。
その後、あの漱石の傑作小説のお茶の味を求めてお茶屋さんを巡り、随分と道草をくった
ような気がしますが、これまで味わったなかで、最もお勧めできると思われる玉露を次に
紹介したいと思います。
日本文化 【お茶 その至福のとき】HOMEへ
|